日本語における「人」の数え方を完全解説!「名」との違いとは?

日本語を学ぶ外国人の方にとって、「人」を数える方法は少し混乱するかもしれません。
特に他の言語とは違う日本独特のルールがあるため、最初は戸惑うことも。
この記事では、日本語の「人」の数え方をわかりやすく解説し、英語との違いや「名」の使い分けも紹介します。ぜひ最後までチェックしてみてください!
Contents
日本語の「人」の数え方とは?基本ルールを解説
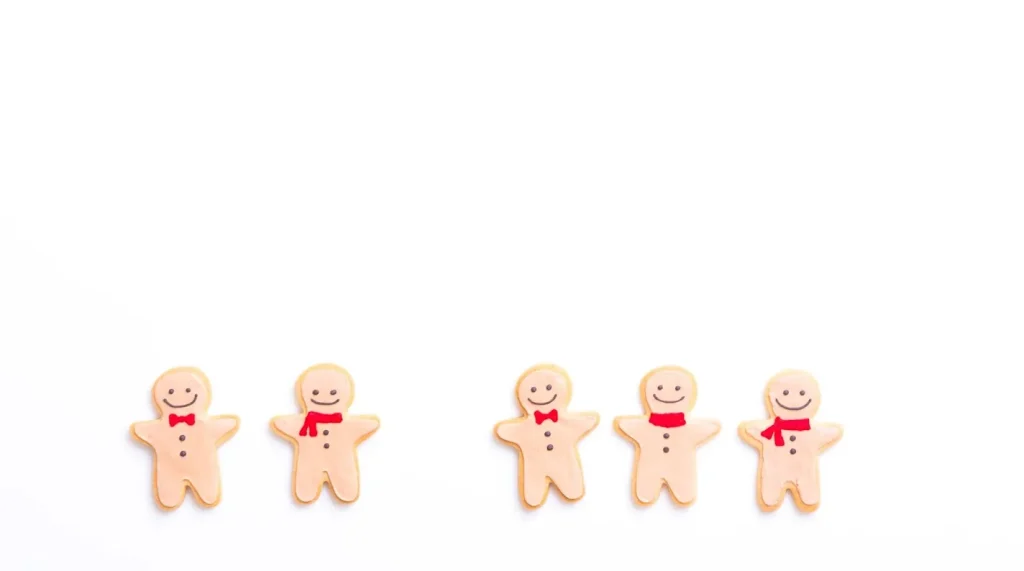
日本語では、人数を数えるときに「人(にん)」という助数詞を使います。
この「人(にん)」は、漢字そのものが「人」を表しているため、覚えやすいでしょう。
① 数字と「人」の使い方
文章で人数を表現する時は、数字の後に「人」をつけるだけで簡単に表現できます。
しかし、口頭で発音するとき、数字によって読み方が異なるため、少し複雑に感じることがあります。
例えば、以下のように読みます:
- 1人:ひとり (hitori)
- 2人:ふたり (futari)
- 3人以降:さんにん (sannin)、よにん (yonin) など
数字によって変わります。
② 4人以上はシンプルに
4人を超えると、読み方はぐっとシンプルになります。
基本的には数字の後に「人(にん)」をつけるだけです。
- 5人:ごにん (gonin)
- 6人:ろくにん (rokunin)
- 7人:しちにん (sichinin) または ななにん (nananin)
\英語とは違う!/
このように日本語では「人」を数える方法が特徴的で、英語の「person」や「people」とは異なります。
最初はちょっと不思議に感じるかもしれませんが、慣れてしまえばすぐに使いこなせるようになるでしょう!
【読み方あり】日本語の「人」の数え方一覧表
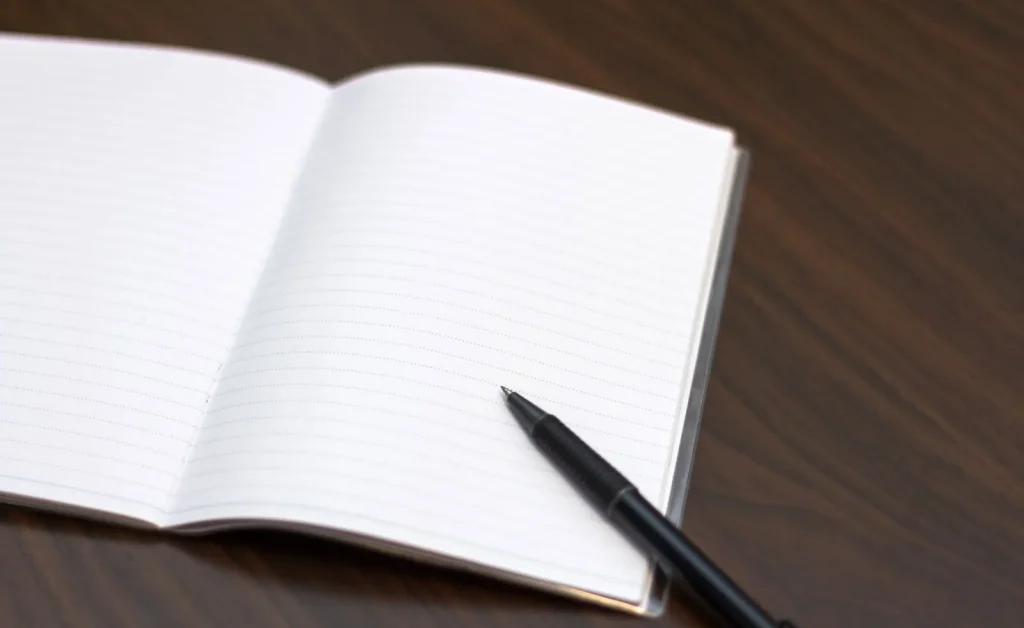
日本語で「人」を数える方法を、こちらの表でまとめてみました。
数字ごとの読み方をチェックしてみましょう。
【人の数え方】
| 数字 | 漢字 | 読み方 | 日本語の発音 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 一人 | ひとり | hitori |
| 2人 | 二人 | ふたり | futari |
| 3人 | 三人 | さんにん | sannin |
| 4人 | 四人 | よにん | yonin |
| 5人 | 五人 | ごにん | gonin |
| 6人 | 六人 | ろくにん | rokunin |
| 7人 | 七人 | しちにん/ ななにん | shichinin/ nananin |
| 8人 | 八人 | はちにん | hachinin |
| 9人 | 九人 | くにん/ きゅうにん | kunin/ kyuunin |
| 10人 | 十人 | じゅうにん | juunin |
| 100人 | 百人 | ひゃくにん | hyakunin |
| 1000人 | 千人 | せんにん | sennin |
| 人数を聞くとき | 何人? | なんにん? | nannin |
1人・2人の数え方と特別な読み方
1人と2人には、ちょっと特別な読み方があります。
- 1人 → ひとり (hitori)
- 2人 → ふたり (futari)
これは他の数字と少し違うので、覚えておくと便利です!
1人と2人だけは、このように特別な形になります。
3人以上の数え方(さんにん・よにん…)
3人からは、基本的に「〇人(にん)」という形で数えますが、4人だけ少し例外があります。
- 4人 → よにん (yonin)
「よんにん」とは言いません!「よんにん」という言い方は、間違いではなくても、通常は使われませんので、「よにん」と覚えておきましょう。
あとは数字に「人(にん)」をつけるだけなので、覚えておけば簡単に使えますよ。
「人」の読み方・発音に関する注意点と間違えやすいポイント
- 「9人」には「くにん(kunin)」と「きゅうにん(kyuunin)」の2つの読み方がありますが、どちらも正しいので、お好みで使ってください。
- 「7人」も「しちにん(sichi nin)」と「ななにん(nana nin)」の2つの読み方がありますが、「しち(sichi)」と発音すると、「1(ichi)」との聞き間違いが発生することがあります。特に電話でのやりとりでは「ななにん」を使うのがオススメです。
これらのポイントは、人数を数える時だけでなく、電話番号や住所を伝える時にも役立ちます。
覚えておけば、いろいろな場面でスムーズにコミュニケーションが取れますよ!
「人(にん)」と「名(めい)」の違いとは?

レストランなどで「何名様ですか?(nanmeisama desuka?)」と言われたことはありませんか?
日本では、人を数える際に「人(nin)」と「名(mei)」という二つの単位があり、場面に応じて使い分けられます。
「名」は、数字の後に続けて「1名(ichimei)」「2名(nimei)」「3名(sanmei)」「4名(yonmei)」と非常にシンプルに発音します。特別な読み方は必要ありません。
では、どのような場合に「人」と「名」を使い分けるのでしょうか?
主な使用シーンは次のとおりです。
- 改まった場面
- 個人を特定できる場合
日本語では「人(にん)」と「名(めい)」を使い分けることがあります。
これ、実は意外と重要なんです!
1. 改まった場面
「名」は「人」に比べて、よりフォーマルな印象を与えます。
たとえば、レストランでスタッフが「何人ですか?」ではなく「何名様ですか?」と尋ねるのは、このためです。
こうした場面では「名」の方が丁寧で礼儀正しい響きになります。
2. 個人を特定できる場合
「名」という単位は、個々の人物を指し示す時にも使います。
これは「名」が「名前」を意味する漢字だからです。したがって、特定の個人や識別できる人物グループを数える時に使われます。
例えば、「卒業生20名」や「従業員100名」など、特定の人々を数える時には「名」を使います。
例外:改まった場面でも「名」を使わない場合
「名」を使わないケースもあります。
例えば、順番を表すときや、料理の量を表すときには「人」を使います。
- 順番を表す時
「〇〇人目」と表現するのが一般的です。例えば、「2人目(ふたりめ)」「10人目(じゅうにんめ)」のように、順番を示すときは「名」ではなく「人」を使います。
ですので、「2名目(にめいめ)」という言い方はしませんので、注意しましょう。
- 料理の量を表す時
レストランなどで料理の量を示す場合、例えば「1人前(いちにんまえ)」や「2人前(ににんまえ)」という言い方をします。
「1名前(いちめいまえ)」という表現は使いませんので、こちらも覚えておきましょう。
「人」「名」以外の人の数え方(者・方)を解説!

日本語では「人」や「名」以外にも、特定の状況に応じて異なる単位を使います。
「者(しゃ)」や「方(かた)」は、特に職業や敬意を表す時に使われることが多いです。
これらの使い方を知っておくと、さらに自然な日本語が使えますよ!
「者(しゃ)」の使い方|職業や属性を表す場合
「者(しゃ)」は、特定の職業や属性を持っている人を指す時に使います。
例えば「技術者1名」や「学生3名」のように、役職や職業を示す場面で便利です。
また、「者」にはその人の立場を表す意味もあります。
例えば「三者面談」では、教員、親、子どもの3者が話し合う場面を指します。
「方(かた)」の使い方|敬意を表す場合
「方(かた)」は、目上の人や尊敬すべき人物に使います。
例えば「お客様1名」や「先生2方」のように、相手に敬意を表す際に使います。
もともと「方」は「方角」や「方法」などを示す言葉ですが、人を数える際には「お一方」「お二方」「お三方」など、より丁寧に表現するために使われます。
よくある疑問Q&A|日本語の「人」の数え方をもっと理解しよう!
日本語の「人」の数え方については、まだまだ疑問がたくさんあるかもしれません。
ここでは、よくある質問に答える形で、さらに深く「人」の数え方を理解していきましょう。
Q1:「人(にん)」と「名(めい)」はどちらを使うべき?
「人(にん)」と「名(めい)」は、状況によって使い分けます。
一般的には、日常的な場面や人数を単に数える場合は「人」を使いますが、個々の名前が特定できる場合や、フォーマルな場面では「名」を使うのが一般的です。
- 例:「今年の新入社員は総勢200名です。」(フォーマルな表現)
- 例:「国立競技場の収容人数は6万8千人です。」(一般的な表現)
Q2:英語の数え方と日本語の違いは?
英語では「person」や「people」を使い分けますが、日本語では「人」や「名」など、文脈に応じて複数の単位を使います。
特に、フォーマルなシーンでは「名」を使う点が大きな違いです。
Q3:「〇人前」「〇人目」にはなぜ「名」を使わない?
「〇人前」や「〇人目」は、人数を示すものではなく、食事の量や順番を指す特殊な表現です。
そのため、これらの表現には「人」を使い、敬語で使う「名」ではなく、一般的な単位として「人」を用います。
まとめ|日本語の「人」の数え方をマスターしよう!
日本語における「人」の数え方には独自のルールがあり、英語との違いに戸惑うこともありますが、基本を押さえておけば、日常会話からビジネスシーンまで活用できます。
「人」と「名」の使い分けや、他の単位(者、方)をしっかり学び、流暢な日本語を目指しましょう!






